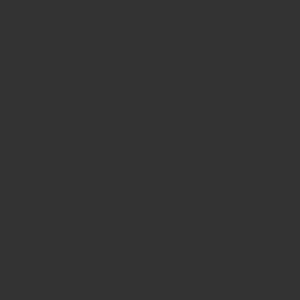
持っていることで、すべての電気工事ができるようになる、電気関係の現場仕事している方からすれば、最終目標の資格です。
東電関係の仕事や大型設備の工事もできるので、電気関係の仕事で困ることはないでしょう。
・大型工場や東電関係の現場仕事の求人で有利
・求人の返金年収は500万~600万
・合格率は筆記試験が50%、実技試験が60%
・試験日は筆記試験が10月上旬、技術試験が12月中旬
・申請期間が6月中旬~7月上旬
・第2種電気工事士を勉強していた私が筆記試験が1か月、実技試験が2週間程度
・資格取得にかかる金額は、工具を持っていないと60000円、工具を持っていれば35000円
第1種電気工事士は、電気工事士の資格の中で最上位の資格になります。
現場作業ではこの資格があればすべての電気工作物の作業ができます。
求人に関しては、電気設備関係の仕事している会社からは、ぜひ働いてほしいと思われるでしょう。
この資格を取得していないと、就職できない大手の工場の求人もあるくらいです。
また免許状の交付には実務経験が3年必要なので、実務経験もある方だと思ってもらえます。
実務経験がない方でも、合格していれば、育てたいと思われますし、実際入社してから資格を取らせる会社も沢山あるので、あまり心配しなくてよいかと思います。
試験概要
試験代は11300円になります。
試験は筆記試験が10月、実技試験が12月にあります。
試験申請期間は、6月中旬~7月上旬になるので、忘れないようにしましょう。
試験問題に関しては、筆記試験と実技試験の2科目になります。
試験時間に関しては、筆記試験が140分で50問、技能試験が60分になります。
筆記試験で、100点満点中60点で合格、実技試験は欠陥がなければ合格になります。
実技試験は筆記試験に合格すると受験できます。
試験結果は約1か月後にホームページで検索でき、そのあと少しして合否通知書が郵送されてきます。
受験方法
公式ホームページから試験を予約しましょう。
以下のサイトで申請できます。
申請期間があるので、忘れないように気を付けましょう。
勉強時間
勉強時間に関しては、筆記試験と実技試験の2科目があり、第2種電気工事士を持っている私が筆記試験は1か月、実技試験は2週間程度になります。
筆記試験に合格すると実技試験になります。
合格した後に少し時間があるので、まずは筆記試験を勉強しましょう。
筆記試験関しては、第2種電気工事士より難しくなっているので、参考書を読むようにしましょう。
基本的には過去問を解くことで合格できますが、実際の設備の写真などを見ないと理解を深められません。
勉強する際には参考書を購入しましょう。
実技試験は60分で電気工作物を施工する試験になります。
あらかじめ解答が公表されている10問のうち1問が試験に出ます。
ですが1つでもミスすると不合格なので、楽な試験ではありません。
私は実技試験の10問中を1通り解くつもりです。
中には2回実技試験練習する方もいるので、2回する方は1ヶ月くらいを勉強時間に見込むと良いと思います。
作業方法ですが、ネットにある情報だけでもなんとかなります。
実際に作成する動画もあるので、参考書を買う必要は無いと思います。
私は、電気工作物を購入したときについてくる施工資料だけで作業する予定です。
資格取得にかかる金額は、参考書代が2000円~5000円、実技試験の電気工作物材料が23000円、実技試験の工具セットが27000円と結構な金額がかかります。
ですが、第1種電気工事士はすべての電気工作物の作業ができるようになるので、多少お金がかかっても取得するべき資格だと思います。
資格取得を目指して何をすればよいか
1.試験日に合わせてスケジュールを立てる
2.筆記試験の勉強
3.参考書を読む
4.過去問を解く→答え合わせ→過去問を解くを繰り返す
5.過去問の正解率が9.5割くらいになるまで解く
6.いざ筆記試験へ
7.筆記試験に合格したら、実技試験の勉強へ
8.実技試験の練習を1通りやる
9.不安な人は、もう1通り
第1種電気工事士は、お金がかかるのと同時に、実務経験がないと免許状を発行してもらえません。
電気設備関係の仕事する方が受験するようにしましょう。
また基本的な電気設備の作業は第2種電気工事士で大丈夫なので、電気関係の事を知らない人は第2種電気工事士を受験するようにしましょう。
第2種電気工事士の記事はこちら
第1種電気工事士はすべての電気設備の作業ができる資格です。
細かい電圧の違いを話してもちんぷんかんぷんになると思うので簡単に紹介します。
第2種電気工事士は電気すべてを扱えるわけではなく、変圧器で100Vまたは200Vに変換した物を屋内に引き込んでいる建物で作業ができます。
この変圧器を自前で設置している会社や工場などでは第1種電気工事士でしか作業ができません。
以上がざっくりとした説明になります。
要は大きい建物では第1種電気工事士が必要になるかもよという話です。
筆記試験に関して
筆記試験に関しては、第2種電気工事士よりもでる範囲が広くなっているので、難しくなっています。
できるだけ参考書は購入したほうが良いと感じました。
合格できる自信のある方は、過去問だけでも大丈夫でしょうが、できれば参考書を購入することをおすすめします。
この参考書は第2種電気工事士でも紹介したように、イラストが多いのでわかり易い内容になっています。
現場を知っている方でも参考書がある方がより勉強に身が入ると思うので、購入して損はないはずです。
参考書の最後に、過去問から選抜した問題集がついているので、それを解くことで、電気工事士の試験がどんなものか把握できるかと思います。
基本的な勉強法に関しては、
1.参考書を一読
2.よく出る過去問を解く
3.わからなかった問題を参考書で見直し
4.ある程度わかるようになった段階で過去問へ
5.過去問の正解率が8割~9割くらいになるまで勉強。
基本的には第2種電気工事士と同じ流れの勉強方法になります。
参考書を読むことで試験範囲の設備の名称や工具、部材に関しての知識を深められます。
参考書を一読した後に過去問を解くことで合格がぐっと近づくでしょう。
参考書の最後についている過去問だけでは、合格に不安が残るので、過去問のサイトも利用しましょう。
第2種電気工事士と同様で、試験センターが過去問を提供しているので、勉強もしやすくなっています。
過去問は3年分くらい解いておけば、合格できると思います。
実技試験に関して
筆記試験に合格したら、次は実技試験の勉強に入りましょう。
実技試験ということで、実際に電材を使った試験になるので、作業しないと受かりません。
なので電気工具と電材が必要になります。
電気工具は、仕事柄揃えてるという方は必要ないと思われます。
また第2種電気工事士で購入した方は、材料の購入のみで大丈夫です。
工具はホーザン一択で良いかと思います。
電材ですが、今回は2回分を載せております。
1回で受かるよという方は、1回分を購入してください。
参考書は、今回は必要です。
なぜかというと工具についてくる実技試験の資料は、第2種電気工事士用になるので、第1種電気工事士には役に立ちません。
ですので、参考書は購入しましょう。
第1種電気工事士の実技問題は全10問になっています。
参考書はカラー写真で作業手順がよく分かるようになっています。
参考書を読んでから実際の作業するのが良いでしょう。
またホーザンからも技能試験対策が出ているので、参考にしましょう。
これは第2種電気工事士の記事にも書いたのですが、実技は細かいことに悩むよりもまずやってみることが大事です。
参考書だけを読んでいると難しい内容に思えますが、実際にやってみると体が覚えるので、ミスを恐れずに挑戦してみましょう。
また動画も参考にしてもらえればと思います。
やってみれば案外体が覚えてくるので、何回か施工を繰り返すのがおすすめになります。
まあ早い話実践あるのみです。
第1種電気工事士の講座
第1種電気工事士の講座に関してはユーキャンがおすすめです。
まとめ
第1種電気工事士の勉強に関してまとめてみました。
基本的には第2種電気工事士と一緒で、筆記試験は過去問、実技試験は実際に作業するスタンスで大丈夫になります。
第1種電気工事士はすべての電気設備が扱えるので、求人も増えます。
実務経験がないと免許状を発行してもらえないので、実務経験が必要になりますが、経験があれば大抵の電気屋さんで雇ってもらえるのでは無いのでしょうか。
電気関係の仕事では無いと駄目な資格になるので、ぜひ取得しましょう。
またどうしても合格できないという方には、講習もあるので参加してみるのも手かと思います。
電気関係の仕事している方にとったら独学で余裕な資格になるので、頑張りましょう。
あまり難しく考えず、過去問と実技だけを勉強すればよいかと思います。
転職情報
第1種電気工事士は東電の仕事もできる資格なので就職する幅はグッと広がると思います。
転職する際は以下のサイトを使ってみるのがありかなと思います。