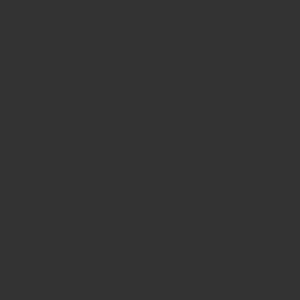この記事に関して
今回は平成31年度1月の過去問の勉強方法について記載します。
基本的な勉強方法に関しては、過去問を解くことなのですが、ただ単に過去問を解くといってもやり方がわからないように思えました。
今回はそんな過去問の解き方を説明していこうかと思います。
平成31年1月分の過去問になります。
まず第2級陸上無線技術士は4科目になっているので、軽く説明させてもらいます。
基礎に関しては、計算問題になるので、基本は計算式を覚えることになります。
この科目に何してはまだ過去問の解き方を作れていないので、作成したらアップしようと思います。
無線工学Aと無線工学B、法規に関しては暗記科目になるので、過去問の勉強方法について記載していきます。
また自分の勉強の仕方についても詳しく説明出来ればと思います。
また過去問に関して解説を知りたいという方は、ぜひ過去問の参考書を購入してください。
法規
まずは法規の勉強方法について記載します。
この科目は4科目の中で一番簡単な科目になっており、計算式などもないので、暗記だけで合格できます。
では実際にどう勉強するのか?
まずは過去問に回答を書いてしまいましょう。
回答を記入した過去問を上げておくので参考にしてください。
これをまず一通り読みましょう。
読む時に気をつけることは、最初は問題の答えを番号で覚えてしまうことです。
番号で覚えることによって回答しやすくなります。
それで何回か繰り返し問題を解いた時に、回答文を読んで覚えるようにすれば、必然的に得点も上がります。
ある程度回答を覚えたら答えのない問題文で勉強しましょう。
問題を見て回答していきましょう。
これを何回か繰り返すことによって、正解の解答と不正解の回答、回答文のどこが間違っているのかがわかるようになってきます。
なので何回も繰り返して勉強していきましょう。
無線工学A
法規の次は無線工学Aに関して、勉強方法を記載します。
無線工学はA、B共に暗記すれば合格できるので、法規同様の勉強法で大丈夫です。
まずは解答が記載してある過去問を上げておくので参考にしてください。
まずはこれに何回か目を通して、回答番号を覚えます。
回答を覚えたら過去問を解いて、点数を出して覚えていきます。
過去問を載せておくので、参考にしてください。
上記の過去問を使って、回答していきましょう。
何回か繰り返すことによって、問題を解いている時に余裕ができて正解以外の回答文を見れるようになります。
なぜ他の回答文が見られるようになると良いかというと、過去問を解いていくとわかるのですが、年度が違う過去問にも同じ問題や回答文が出てくる時があります。
その時に回答文が少しだけ違う場合があります。
その時にも他の回答文を知っていれば、間違いの選択肢と同じ回答文の場合は間違い。
回答文が少し違う場合は、正解と回答を絞れます。
なので、何回も過去問を解くことが大事になっていきます。
無線工学B
最後に無線工学Bの過去問を載せておきます。
無線工学の基礎に関しては、この記事が色々な人に見てもらえて、参考にしてもらえるようでしたら、過去問の解説を書いてみようと思っております。
次に回答が載っていない過去問を載せておくので参考にしてください。
まとめ
今回は平成31年 1月分の過去問の勉強方法を記載しました。
無線工学の基礎に関しては、この記事を参考にしてくれる方が多ければ記載しようと思っております。
基本的に第2級陸上無線技術士は過去問を勉強すれば何とかなります。
基本的な勉強方法に関しては以下の記事に詳細を書いているので、参考にしてもらえればと思います。